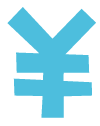電子マネーと仮想通貨の違いとは?フィンテックが活発になる前に知っておきたい基礎の基礎
目次 |
1.ビットコインは悪者か?フィンテック、仮想通貨をめぐる日本の消費者の態度とは?
●ビットコインのイメージは?
仮想通貨やビットコインと聞くと、どのような印象を持たれるでしょうか?
「仮想通貨?お金ではないんでしょ?ゲーム上のマネー?」
「ビットコイン?手を出してはいけない闇の取引き?」
「不正利用されてしまうのでは?」
「ネット上での取引にセキュリティの問題はないの?」
など、まるで手を出したら最後!一生を狂わせかねない恐ろしいもののように考えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか?
では、仮想通貨は、人々に損害を与える悪者という認識に誤りはないのでしょうか?
●ビットコインに悪者イメージを付けた「Mt.Gox社」の事件と報道とは?
ビットコインと聞いて、日本人が真っ先に思い浮かべるのは2014‐2015年にかけての「Mt.Gox社」の一連の報道ではないでしょうか。
日本国内の消費者に「ビットコイン=悪者」というイメージが定着してしまった原因は、この「Mt.Gox社」の事件と報道によるものが大きいと言えます。
では、なぜそのようなイメージが、日本国内の消費者についてしまったのでしょうか。
「Mt.Gox社」とは、東京、渋谷に本店を構えていたビットコイン取引所です。
2009年にトレーディングカードのオンライン交換所として開設された「Mt.Gox社」は、2010年にビットコイン取引所に事業転換しました。
そして、事業転換後の2011年に、後に問題を引き起こすことになるマルク・マリ・ロベール・カルプレス氏(MarkMarieRobertKarpelès)に会社を売却しています。
これによって、カルプス氏は「Mt.Gox社」の経営権を獲得し、同社のCEOとなったのです。
以降、「Mt.Gox社」は、日本でビットコインを円と交換できる唯一の取引所として知られ、2013年、カルプス氏のCEO就任からわずか数年で、ビットコイン取引量の70%を占める世界最大の取引所までに発展したのです。
このように「Mt.Gox社」は、わずか数年にして大きく成長を遂げた国内でも有名な取引所であったわけですが、日本国内の消費者に「ビットコイン=悪者」というイメージをつける大きな事件がこの後すぐに起きることになります。
それが、2014年2月の「Mt.Gox社」のサイバー攻撃による盗難被害のニュースです。
上記のように、世界的に大きく飛躍した「Mt.Gox社」は、その絶頂期の中で、同社が保有する約85万ビットコインをハッカーによって盗まれ、莫大な損失を受けたという非常にショッキングな報道が上がってきました。
その額は、日本円にして200億円以上とも言われていました。
これによって、同社は、民事再生法の適用を申請し、その後、破綻しています。
一方、「Mt.Gox社」の破綻によって、富を失った数万人の債権者は、同社に対し数百億円の請求を行うも、そのうち返済されるのはごくわずかだと言われています。
一般の消費者にとって、このニュースは、非常にセンセーショナルな事件だったに違いありません。
また、ビットコインという名前をこの報道によってはじめて知ったという方も多かったはずです。
日本国内の消費者の多くが、未だに仮想通貨を信用できないものとして認識している背景には、これらの報道が深く関係していると言えるでしょう。
それは、日本で初めて「仮想通貨」自体を広く一般に、そして、大々的に知らしめたのが、このニュースだったからです。
さらに、国内の消費者の「仮想通貨」のイメージを悪くさせる原因はこれに留まりませんでした。
それは、「Mt.Gox社」CEOのカルプレス容疑者逮捕の報道です。
2014年に同社が保有するビットコインは、ハッカーによって盗まれたと言っていたカルプレス容疑者でしたが、実際は自身が社内システムを不正操作し、自分名義の口座を水増、
顧客の預金を着服したとして、2015年8月に業務上横領の容疑で逮捕されたのです。
この報道によって、ビットコイン自体もさらに注目を集めることとなりました。
上記のように、実際には「Mt.Gox社」が破綻、その要因はカルプレス容疑者にあったわけですが、過熱する連日のニュースによって、いつしか仮想通貨やビットコインは信用できないもの、そして「ビットコイン=悪者」という構図が国内の消費者の深層に深く根付いていったことは間違いありません。
●悪者は「仮想通貨」ではなかった!
ただ、ビットコイン自体は、「Mt.Gox社」が破綻した後も稼働していました。
そこに消費者がなぜ、ビットコインは消滅、あるいは手を出してはならないものとしてイメージを内面化してしまったのか、その原因の一端が隠れています。
それは、報道側と消費者側、それぞれの情報の扱い方、受け取り方の食い違いにありまし
た。
消費者側がビットコインに決して手を出してはならないという認識を持ってしまったのは、ビットコインのシステム自体、また「仮想通貨とは何か?」といった十分な知識を持たないままに、「Mt.Gox社」の破綻と容疑者逮捕の報道のみを見たということが一点。
もう一点は、報道する側が仮想通貨やビットコインに関する基礎的な情報を提供することができていなかった、あるいは、きちんと伝えることができなかったために、消費者に的確な情報が伝わらなかったということでしょう。
その結果、情報と認識の不一致が起こり、あたかもビットコイン自体が悪者のように消費者には捉えられてしまったのではないでしょうか。
報道によって「Mt.Gox社」は破綻したと報じられたわけですが、ビットコイン自体が破綻したわけでも消滅してしまったわけでもないのです。
さらに、「Mt.Gox社」がビットコインのシステムを開発したわけでもなく、世界のビットコイン自体を発行していたわけでもないのです。
「Mt.Gox社」は、ビットコインにとって単なる取引所です。
世界中にいくつも設けられているビットコイン取引所の1つということになります。
ですから、「Mt.Gox社」が破綻しても、同社のCEOが逮捕されても、ビットコイン自体の動きには、何ら影響はないということになるのです。
その構図を簡単に言えば、コンビニエンスストアー1店舗が経営悪化によって閉店したとしても、チェーン店のすべてが閉店してしまうわけではないということと同じです。
そういったことが、消費者には上手く伝わらず、ビットコイン自体が消滅してしまったと思わせてしまったのです。
●「仮想通貨」と将来の生活
実際、事件後もビットコインは順調に稼働し続け、これまで順調な動きを見せてきました。
かつて、日本に本社を置くビットコインの国内取引所は「Mt.Gox社」一社のみでした。
それが、2014年以降、増え続け、現在では、10社近くのビットコインの取引所が営業を行っているのです。
さらにサービスも拡大、時価総額は大きく増え続け、現在では、世界で約1兆円に迫る勢いを見せています。
大きな事件と報道以降もビットコインは稼働し続けたという状況は、以前からのビットコインユーザー、あるいは正しい知識を持っていた方にとっては、セキュリティー上のリスクや突発的なアクシデントなどにも柔軟に対応できるというこの堅牢性にむしろ注目が集まったと言えるでしょう。
ビットコインや仮想通貨という言葉と同時に、よく聞かれるのが「フィンテック」という言葉です。
この「フィンテック」自体も、上記の一件からあまりいい印象を持たれていないという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には、「ビットコイン=悪者」という認識が誤ったものであるように、「フィンテック」も私たちの生活を脅かすような悪いものではないのです。
ビットコインがそうであったように「仮想通貨」や「フィンテック」は、自分たちの暮らしには無関係、ネットのスターシステムに関わる一部の特権階級のものにすぎない、そのように思われていらっしゃる方も多いかもしれません。
しかし、今後フィンテックが活発化すると、この仮想通貨は近い将来、自分たちの暮らしの身近にあり、なくてはならない存在となるかもしれないのです。
近年、このフィンテックが金融革命を起こし、金融形態を根底から突き動かす事態に発展するだろうと予測される中で、もはや金融業界のみならず、個人レベルでも対岸の火事と俯瞰するに留まらない状態が迫っていると言えるでしょう。
日本の経済や流通、消費者の日常の生活を支えてきた銀行のその知的業務が、瞬時に処理が可能な新技術の導入や人工知能に置き換えられようとする中で、IT主導の金融業界が形成されていくのも時間の問題かもしれません。
さらに、フィンテック革命を前に、その波はITを身近に据える一部の人たちや企業のみに関連するに留まらず、国や個人の生活にも影響を及ぼすような大きな改革が、既に身近に起こり始めているのです。
2.仮想通貨、国内での位置づけは?電子マネーとどこが違うのか?
実際に私たちは、「フィンテック」の片鱗を身近に捉え、それを「フェンティック」の恩恵と知らずに、便利なツールとして日常の中で利用していることがあります。
そのわかりやすい例が、電子マネーです。
2-1電子マネーと仮想通貨はどこが違うのか?
●「リアルマネー(通貨)」「電子マネー」「仮想通貨」
「電子マネー」という言葉から具体的なイメージを見つけることができないという方でも、「Suica」「nanaco」「WAON」「おサイフケータイ」などというと聞いたことがある、あるいは利用しているという方も多いのではないでしょうか。
この「電子マネー」は、インターネットが一般に普及したことによって、登場し、利用可能になったものです。
また、一方で「仮想通貨」においても同様に電子技術の進展によって発達してきたものです。
「電子マネー」も「仮想通貨」も、コンピュータの情報通信技術が発達したことによって利用可能になったサービスで、現在ではその種類や国によって、一部限定的ではあるものの、その利用可能な範囲内においては、インターネットの技術を通してモノを購入することができるという点で共通しています。
さらに、それぞれと同時並行的に発展し、双方の発達に必要不可欠であるものとして「フィンテック」がありますが、それらについては、以降、詳しく説明するとして、ここでは、まず、「電子マネー」と「仮想通貨」に違いはあるのか?ということについてまとめていきたいと思います。
まず、「電子マネー」も「仮想通貨」も、その発達段階において国家レベルで、さまざまな分野の有識者や研究者を交え、それぞれの位置づけや取り扱い、貨幣機能との違いなど議論が取り交わされてきました。
そのような中で、常に議論の中心となってきたのは、「法定通貨とどう違うのか?」ということです。
仮に貨幣が貨幣であるための手段として、また、電子マネーや仮想通貨が、決済に利用可能な価値交換ツール、サービスや商品流通の媒介物として認知されているとするならば、法定通貨のように国によってその価値を保証されるリアルマネー(通貨)と電子マネー、仮想通貨は、どのような違いがあるのでしょう。
法定通貨が、紙や金属といった一定の形状を取った時代から、「貨幣とは何か?」という疑問は国家を超え、長い歴史をかけて、さまざまな思想家、経済学者、哲学者が、分野の垣根を超えて研究してきた分野でもあります。
そして、現在でもなお、主要研究分野として、研究に取り組んでいる人たちがいるほど、未だ議論の余地のある分野であり、新たな類似通貨システムの進展も相まって、さらなる議論が展開されることが期待されているところです。
さらに、このような状況にあるからこそ、定義についても視点によって揺らぎがみられるという点は否めません。
●「通貨の機能」と「電子マネー」「仮想通貨」の共通点と相違点
しかし、ここでは上記を加味した上で、疑問に対する理解を容易にするために、あえて比較の手段として、一般的に言われてきた通貨の定義を使用して、「電子マネーと仮想通貨は、リアルマネーとどう違うのか?」「電子マネーと仮想通貨の違いとは?」を見ていきたいと思います。
一般的に通貨は、以下の3つの機能から定義されます。
その機能は、1.「価値の尺度としての機能」、2.「交換(支払)手段としての機能」3.「価値貯蔵手段としての機能」です。
しかし、ここではそれらの機能とは別に、社会一般に通用する通貨として機能させるためになくてはならないポイントとして4.「信頼性とコモンセンス」を付け加えておきたいと思います。
1.「価値の尺度としての機能」
まず、「価値の尺度としての機能」とは、簡単に言えば、物の価値を瞬時に理解することができるものさしのような役割です。
ここでは、この「価値の尺度としての機能」について、「法と発達要因」「発行者(管理者)は誰か?」「発行総数と投機性」からリアルマネー(通貨)、電子マネー、仮想通貨について探ってみたいと思います。
●「法と発達要因」
官から民へというように、法律が先行する日本においては、法律は何事にも優先されるもので、この価値の尺度についても同様のことが言えるでしょう。
では、「電子マネー」と「仮想通貨」は上記の点において、共通する点はあるのでしょうか?
先にも述べたように「電子マネー」と「仮想通貨」は、コンピュータの情報通信技術の発達が、大きな要因であることは言うまでもありません。
そして、このことによって利用可能になったサービスであるという点でも共通していると言えるでしょう。
さらに、それぞれが、硬貨や紙幣ではなく電子的なデータによってやり取りが行われること、国内では外為法など狭義での法適用を除き、広義では「資金決済法」という法律に拠るところが大きいといった点でも双方は共通しています。
この「資金決済法」によって、両者は、「財産的価値」があり「公的な決済手段」に利用できると位置づけられていますが、実際には、「電子マネー」と「仮想通貨」は、完全にイコールではありません。
また、日本国内で発行された日本円(紙幣や硬貨)は、免税店や一部のサービスを除いては、原則として、国外で利用することが難しいといったリアルマネーの特性は、チャージ式の電子マネーにも共通しています。
しかし、仮想通貨は?というと、仮想通貨を受け入れているという前提が必要ではあるものの「海外では通用しないのではないか?」といった心配をすることなく、瞬時に国境を飛び越えることができるのです。
そして、ドルやマルクといった通貨単位に関係なく世界中のどこでも支払いに利用することができ、どの通貨とも交換することができるのです。
日本円のみを持って海外に行っても、両替所での換金の手間もなく、スマートフォン一つで世界共通の価値を交換し、決済できるという点でも仮想通貨は、まさに未来型と言えるでしょう。
上記の点において、リアルマネー(通貨)や電子マネーに対する仮想通貨の違いが見えてきましたが、その違いは、それらを誰が発行し管理しているか?という点にも表れています。
●発行者(管理者)は誰か?
上記のように「電子マネー」も「仮想通貨」も、国内の法の上では「公的な決済手段」として認識され、硬貨や紙幣ではなく電子的なデータによってやり取りが行われるものという点では共通しています。
しかし、それらを発行し、管理を誰が行っているのかということについては、位置づけが全く異なっています。
まず、一般的に利用されている電子マネーは、日本銀行で発行している「日本円」を利用していますが、仮想通貨には、国や銀行といった発行元があるわけでも管理主体があるわけでもありません。
ですから、仮想通貨は、日本円だけではなく、利用可能とされるエリアであれば、海外でも米ドルや中国元のように利用することが可能なのです。
●発行総数と投機性
また、仮想通貨は、発行総数が決まっているということも特徴の一つです。
だからこそ、希少価値があり、その価値には、日々動きがあるのです。
これについては、一点の絵画の取引とその価値を想像するとわかりやすいかもしれません。
はじめは、価値をつけることができず、1円である人が売却したとします。
数年後、作者にブームが起き、作者の描いた絵画を探す大勢の人が出てきたら、どうでしょう。
絵画は、一点限りです。
話題性と作者のもつ社会的価値とそれらが生み出す信頼性によって、絵画の価値は上がり、それを欲しいという人が大勢存在すれば、競争で値を付けるために、さらに価値は上がります。
このような状況は、ビットコインにも起こりました。
当初、その価値はないも同然だったビットコインは、一時期、100倍という高値に高騰したのです。
ですから、この価値についても、法定通貨と同価で交換可能な電子マネーと日々レートが変動し、投機的意味合いを持ち合わせている仮想通貨とは、全くの別モノのように見えます。
具体的には、日本国内で考えれば、◯◯円=◯◯ビットコイン(以下コイン単位はBTC)と価値が固定されていないからです。
このようなことから、仮想通貨は通貨のかたちをとった投機目的の金融商品であるという意見も国内では多く見受けられます。
しかし、対海外という視点に立った時、外国為替のレートは日々変動するものです。
それでも、ドルや元は通貨としての認識があるのではないでしょうか?
このように考えると、レートが変わるからと言って、通貨ではないとは断定はできないようにも思えます。
確かに、りんご1個が、一昨日は250円、昨日は800円、今日は108円でとなってしまうと、さて、りんごの価値はいったいどの程度なのか、それらに当てはめて価格を考えるとその他の商品の価値さえわからないということになってしまうでしょう。
そのようなことが通貨に起きたとするならば、「価値の尺度としての機能」は果たされていないということになるでしょう。
為替レートであれば、りんごの例のように急激な動きは見られませんが、仮想通貨であれば、可能性はあるのかもしれません。
このように、少し比較してみただけでも、いくつもの違いが見られる電子マネーと仮想通貨ですが、そこに通貨を照らし合わせることで、両者を消費者が安心して利用するためには何が必要か?その改善点と議論すべき点が浮かび上がってくるのです。
しかし、2017年施行予定の改正資金決済法の仮想通貨の位置づけには、通貨や外国通貨とは同等でないと記されているのです。
いずれにしても、技術が法律を追い越している今、法の施行後も早急に方向性を決定していかなければならない課題がいくつか残されているということは確実に言えることでしょう。
2.「交換(支払)手段としての機能」
通貨の「交換(支払)手段としての機能」とは、さまざまなサービスや商品と交換するための媒介物という役割を持ち、支払いができるという機能のことを指しています。
ここでは、電子マネーと仮想通貨それぞれの利用方法を確認し、貨幣の持つ交換手段としての機能があるのか否かについて見ていきます。
●利用方法
まず、電子マネーとは、紙幣や硬貨ではなく、お金の価値を持つ電子的なデータを通貨の代わりに利用することよって決済を可能にし、サービスや商品を購入できるものです。
この決済方法には、インターネット上で取り引きを行うサーバー型と、クレジットカードのような形状でICチップが埋め込んであるカードに金銭的価値、つまりお金のデータを入れそのカードを支払先のリーダー(データ読み取り機)にかざして支払いを行う方法があります。
また、支払いには、先払いと後払いの方法があり、利用前にチャージ(あるいは、自動チャージ)したカードを使って先払いするものをプリペイド型、チャージではなく、クレジットカードなどからの引き落としを利用して後払いでサービスや商品を購入するポストペイ型があります。
なお、以下ではプリペイド型を中心に言及していきます。
上記のように、電子マネーの決済は、電子的なデータのやり取りによって成立するわけで、その電子的な情報は、金銭的価値であり、元をただせば、国内に流通する通貨ということになります。
ですから、日本であれば日本円が、交換(支払)手段として利用されているということになります。
一方、ビットコインなどの仮想通貨は、PeertoPeer(以降P2P)に代表されるように、中央に管理サーバーを置かずに個々の端末同士で情報を共有できるネットワークを用いています。
これと同時にブロックチェーン技術を使うことで、情報を分散管理し、元データを推測できないようハッシュや公開鍵暗号、電子署名などさまざまなシステムを駆使し、偽造や不正利用、作動停止を防止しています。
中央管理がない上に、新しい技術を利用していることから、一見、大変難しいシステムのようにも見受けられますが、中央管理がないからこそ、耐久性に優れ、ビットコインに代表される仮想通貨は、このシステムによって、突発的なトラブルにも対応できるようになっているのです。
さらに、仮想通貨の利用方法は、以下のようになります。
まず、円やドルなどの法定通貨を利用して、銀行振り込みやカード決済を使って、仮想通貨取引所、発掘サイト、あるいは、ウェブ上の集会やトレードサイトで、取引相手を探し、個人取引によって仮想通貨を入手します。
詳しくは後で説明しますが、この時、仮想通貨の保存場所として「ウォレット」と言われるお財布を先に作成しておきます。
そして、入手した仮想通貨を「ウォレット」に入れ保管するという流れです。
さらに、日本国内では、まだまだ限られた範囲でしか利用することができませんが、実店舗で仮想通貨を利用して支払いを済ませたいという場合には、専用アプリを使って、簡単に支払いが可能です。
さらに、交換(支払)手段として、日本以外の国でも利用できるという点は、仮想通貨の特徴であり、電子マネーとの違いです。
また、電子マネーでは、原則的に法定通貨への換金はできませんが、仮想通貨は、取引所やATMを利用して円やドルなどの法定通貨に換金することができますので、価値が上がったところで売却するということも可能です。
このように、換金性の有無も電子マネーと仮想通貨の大きな違いと言えるでしょう。
そして、現段階では、円を取得するにも電子マネーを利用するのにも課税はありませんが、
現時点では、仮想通貨は課税対象であるという点もリアルマネーや電子マネーとの違いです。
さらに、上記でも触れましたが、日本円を海外に送金するという場合に、仮想通貨の威力は発揮されます。
まず、価値の交換手段として、瞬時に国境を超えること。
また、そのスピードに加えて、手数料も安価であるという点です。
リアルマネーの場合、円の送金には、高い手数料がかかり、時間がかかりましたが、これを仮想通貨に換えることで、それらの問題も解決されるのです。
もう一点、電子マネーについて言えば、発行元や加盟店での利用は可能であるものの、チャージしたマネー残高を利用して、他の個人利用者へ移転することはできませんが、仮想通貨に関しては、それが可能です。
これらのように、対応可能なエリアや店舗であれば国内外を問わず、交換(支払)手段として利用できるという点で仮想通貨は、国際社会に必要な機能を兼ね備えたものということになるでしょう。
3.「価値貯蔵手段としての機能」
通貨の「価値貯蔵手段としての機能」とは、現段階での価値を維持し、時間を超えて保有できる機能のことです。
紙幣や硬貨を思い浮かべるとわかるように、法定通貨と呼ばれるものは、紙や金属によって形作られた物理的形態を取っています。
このことは、海外の金融市場を見ても法的な位置づけを見ても明らかです。
また、当然のことながら、認知度の上昇は、信頼性やコモンセンスと深くかかわっています。
世界的な視野で見ると、仮想通貨、特に代表格のビットコインは、破竹の勢いを見せています。
このビットコインを例に、欧州での動きに注目して見てみると、日本国内での認知度と理解力の低さが露呈することになるでしょう。
スイスの「NeueZürcherZeitung」やドイツの「Finanzen.net」と言えば、欧州でも有名な金融メディアサイトです。
最近、この「Finanzen.net」に掲載された為替レート表には「米ドル、日本円、ポンド、スイスフラン、ロシアルーブル、ビットコイン、中国元」と主要通貨の欄に「ビットコイン」が入ったとして話題になりました。
また、欧州では、Finanzen.netだけではなく主要金融メディアサイトが次々と為替レート表にビットコインの欄を加えているのです。
主要国際法定通貨に、ビットコインを並べていることから窺えるのは、欧州内で、「ビットコイン」が基準通貨と同様との認識が広がっているということではないでしょうか。
また、既述したようにビットコインは発行元も管理主体も存在しないものです。
通貨が、中央銀行によって管理され、そのことによって信頼性が人々に内面化されている一方で、そのビットコインが、なぜ稼働し続けることができるのかは、そのシステム自体が「信頼」の根拠となっているからなのです。
一方、電子マネーは、カードやキーホルダー型などの媒体に金銭の電子情報を取り込んだもので、上記に示したように元を正せば、媒介物として利用されるのは、中央銀行が発行した通貨であって、利用状況は、発行者あるいは、中心主体が管理しています。
では、貨幣は形があり、実際に触れることができるからこそ、保存性が高いように思われてもいますが、実際のところはどうなのでしょう。
お金が破れ粉々になった、火事で灰になった、また、貯金していた金融機関が倒産したなど貨幣の「価値保存」に関しても心配なことはあります。
これらについて、日本銀行では5分の2未満のものは貨幣としての価値がない、金融機関の倒産に関する貯金の返金に関しては、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットの可能性もあるとしています。
このように、時間を超えて保有できる価値にはリスクも伴いますが、まずは、貨幣を銀行に保管するように、電子マネーや仮想通貨も価値を保管することができるのか、保管場所はどのようなものなのかを以下に見ていきます。
●保管方法
日本円の保管は、銀行口座または、自宅、お財布で管理している方がほとんどだと思います。
一方、電子マネーの保管場所は、カード型、リストバンド型、キーホルダー型、コイン型などさまざまなものが登場してきています。携帯やスマートフォンにアプリを入れて使うおサイフケータイタイプであれば、ネット上にその価値を保管しておくことができます。
また、ビットコインはインターネット上の仮想通貨なので、物理的な保管はできません。
しかし、電子的データを取引所で専用のウォレットを作成し、管理・保管することはできます。
それが、俗に言われる「ウォレット」です。
そして、仮想通貨を入手する前に、必ずそれらを作成しなければなりません。
さらに、その「ウォレット」には、いくつか種類があります。
保存性やセキュリティの面で若干の違いはありますが、その代表的なものとしては、パソコン上に保存するデスクトップウォレット、web上に保存するオンラインウォレット、携帯、特にスマートフォンのアプリなどを使うモバイルウォレット、アドレスと秘密鍵を紙に印刷して保存するペーパーウォレット、専用端末を別途購入して保存するハードウェアウォレットです。
そもそも、仮想通貨(ビットコイン)のシステム自体、改ざんが事実上不可能なこと、経済不況に強いものですので、その点では、既に物理的形態をとる貨幣に勝っているのかもしれません。
ですから、今後さらに、確固としたセキュリティ体制が容認され、盗難等のリスクが100%ないという確実性が社会に広まったとするならば、仮想通貨が、破損や金融機関の倒産のリスクのない貨幣を上回るものとして存在できる可能性がないとは言い切れないでしょう。
●時間を超えて保有できる価値とは?
しかし、上記のようなリスクを回避できたとしても、一定の価値を長期的に保有することができるのかという点では、仮想通貨は貨幣に劣ると言わざるを得ません。
「発行総数と投機性」で述べたように、仮想通貨に投機性があるということは、その価値が暴落すれば、変容しない財産価値の保証はできないというリスクを抱えていることは間違いないからです。
また、電子マネーについても、特にチャージ型の電子マネーは、発行元の企業が倒産した場合、一定期間の保証はあるにせよ、永遠に払い戻しをすることは不可能ですので、こちらも長期的な財産価値の保存という点で、リアルマネーには劣っているかもしれません。
ただし、仮想通貨が投機性によって一定の価値を保つことができないとしても、上記のような貨幣のリスクを総合的に加味すれば、リアルマネーも同様のリスクがあると言えるのかもしれません。
4.「信頼性とコモンセンス」
20世紀の経済学に革命を起こしたと言われるイギリスの経済学者ジョン・メイナード・ケインズは、貨幣について万人が受容できる信頼性によって、はじめて貨幣が貨幣として機能するとし、誰からも信頼されることの重要性を説いています。
リアルマネーのように万人からの信頼性を電子マネーや仮想通貨が持っているかと問われれば、特に仮想通貨は、Mt.Gox社の一連の動きからも、その域まで達していないと言えるのではないでしょうか。
永続的な信頼性というものが存在するのかということについては、別の分野の専門家にお任せるとしても、現在のリアルマネーのような信頼性を得るためには、まず、「万人」と言えるくらいの利用者数と安全だという認識が共通認識として社会通念に浸透し、人々の深層に内面化されるくらいでなければならないでしょう。
それには、まず、認知度と利用者数が重要になりますが、電子マネーや仮想通貨は日本国内で、どの程度通用するものなのでしょうか。
法律上で「電子マネー」が認知されることになったのは、1997年の外国為替及び外国貿易法(通称:外為法)の改正によってです。
その後、2000年前半から後半にかけて、「電子マネー」は急速に一般に広まるようになります。
そして、少し古くなりますが、2016年の日銀調によれば電子マネーの決済件数は、51億9,200万件、決済総額は、5兆円強とこれだけの統計を見ても、利用者の多さと大規模なサービスへと発展していることが窺えます。
一方の「仮想通貨」は、1995年以降、世界で未来の通貨を予見する論などが出てくるなど専門家内での動きはあったものの、実際にビットコインなど仮想通貨を代表する概念が生まれ、現在のような通念で動き出したのは、2008年-2009年以降と言えるでしょう。
さらに、2016年の国内取引高は、2,610万BTCで、ユーザー数を見てみると日本国内で最大規模の取引所「bitFlyer」のみで、20万人を超えています。
しかし、この数字は、海外での取引数とは比較にならない程低い数字で、国内に普及する電子マネーと比較しても、その認知度やユーザー数において国内での「仮想通貨」をめぐる動きは若干遅れを取っているというところでしょう。
しかし、範囲を広げ、世界という視点に立ってみると、日本の電子マネーに比べ、世界に通用する仮想通貨の認知度は、高く広いと言えるのです。
体が、万人には理解されていないという状態が続くのであれば、それらが国内において通貨に飛躍することは、難しいのかもしれません。
ただ、ほんの数年で、人々の価値観が変わるような実情がこのIT社会にあることを踏まえれば、ビットコインが万人に受容され、通貨の仲間として考えられるような共通認識が人々に流通し、社会通念として昇華していくことも考えられなくはないでしょう。
●「仮想通貨」は、既存の通貨の概念で比較していいものなのか?
しかし、上記のようにリアルマネーや電子マネーと仮想通貨を比較していく中で気づかれた方もいらっしゃるかもしれませんが、そもそも仮想通貨とは、暗号通貨であって、「暗号」による電子的な決済手段であるという点において、既存の「通貨」という概念から突き抜けたものなのです。
言い換えれば、電子的であっても決済手段に成り得るという点から、それと近しい既存の「通貨」の定義や概念と比較せざるを得ない状況があり、政府もそれによる法改正もそれらを軸に検討されてきたわけですが、概念が違う仮想通貨を既存の枠から検討するということ自体をまずは考え直さなければならないのではないかということです。
通貨という概念が生まれる以前は、物々交換や物品交換によってものの交換がなされていました。
これから、バーチャル化が日常生活にも入り込んでくるという時に、石やきれいな貝殻などとの交換まで議論を退行させるのは少々乱暴ではありますが、通貨の概念から外れたところに、政府が整えるべき法の軸となるもの、仮想通貨の発展の鍵が眠っているような気がしてなりません。
2~2仮想通貨出現の背景
●ビットコインの開発者は誰か?
まさに破竹の勢いを見せるビットコイン。
このビットコインの開発者は、ノーベル経済学賞を受賞できること間違いなしと囁かれています。
しかし、ビットコイン開発に関する最大の謎は、開発者が誰なのかが分からないことなのです。
2008年、Cryptography(暗号化)メーリングリストで、ビットコインの原案となる論文は発表されました。
論文タイトルは、”Bitcoin:APeer-to-PeerElectronicCashSystem”(日本語に訳すと「ビットコイン:P2Pネットワークを利用した電子通貨システム」といったところでしょうか)。
そこに署名された発表者は、SatoshiNakamoto(サトシ・ナカモト)という人物です。
SatoshiNakamotoという名前は、一見すると日本人名のように見えますが、実際には、本当に日本人なのか、国籍や性別、どのような職業の人物なのかなど、その正体は未だ謎に包まれたままなのです。
その人物像をめぐっては、日本人研究者なのではないか?アメリカの大学教授では?また、複数の人物がグループで原案を作ったのではないか?と各国でさまざまな憶測が飛び交い、その上、自分が「SatoshiNakamoto本人だ」と名乗る人物も登場し、世界中のメディアを巻き込んで大変な盛り上がりを見せてきました。
ただ、論文に添付されている参考文献には、そこにあえて載せていない文献や思想などを含めて、人物を特定できるような大きなヒントが隠されているのかもしれません。
名乗りを上げた人物が、ビットコイン提唱者であるかどうかはわかりませんが、ビットコイン自体が、特定の発行者を持たないシステムであるのと同様に、提唱者も特定ができないままにシステムのみが稼働し、発展を遂げているのです。
開発者不在のままのシステム稼働は、話題性とメディアの盛り上がり、さまざまな広がりを意図し、提唱者自身が、あえて望んだ方法だったのかもしれません。
●”Bitcoin:APeer-to-PeerElectronicCashSystem”の発表とその後
では、SatoshiNakamotoと名乗る人物が発案した”Bitcoin:APeer-to-PeerElectronicCashSystem”とは、どのようなものなのでしょう。
英文でわずか9枚程度と論文としては短いものではありますが、その中にこれまでの金融取引のシステムでは難しいとされてきた堅牢性に優れた電子取引システムが提案されているのです。
仮想通貨(暗号通貨)は、P2Pネットワークによって分散処理され、暗号技術との組み合わせによって、偽造したり、情報を書き換えたりできないようにできています。
このシステムを利用すると、これまでセキュリティや信頼性の面でどうしても金融機関を通して取り引きを行わなければならなかった個人対個人の電子取引が、第三者機関を必要とせず、なおかつ、安心で安全な取引を可能にできるというものでした。
“Bitcoin:APeer-to-PeerElectronicCashSystem”の発表からわずか3か月後の2009年1月には、論文に触発された多くの研究者や開発者によって開発されたプログラムのソースコードが公開され、その後すぐにビットコインが発行され、初めての取り引きが行われています。
このようにして、ブロックチェーンの最初のブロックが誕生し、SatoshiNakamotoからソフトウェア開発者であるHalFinneyへビットコインが渡ります。
2009年のこのやりとりが、世界で初めてのビットコイン送信です。
ただ、この時点では、本格的な経済市場の参入や利益を目的としたものではなく、論文の整合性を図るための試運転といった意味合いが強かったと言われています。
さらに、同年10月、NewLibertyStandardによって、ビットコインと法定通貨の交換レートが初めて提示され、数日後同社は、日本円で1BTC約0.07円のビットコインを5050BTC、5.02ドルで購入しました。
これがビットコインと法定通貨の初めての取り引きです。
それからおよそ1年後の2010年2月に、ビットコイン両替ができる最初の取引所が誕生しました。
そして、同年5月には、はじめて現実社会でビットコインを使った決済が行われています。
その後、実店舗で初めてビットコインが利用されたのが、2010年5月のことです。
この時の商品は、ピザ2枚分、それを10,000BTCで購入、決済が行われたのです。
同年には、アメリカで有名なインターネットサイト「Slashdot」に掲載されたことをきっかけに、わずか一週間足らずで価格は、1BTC=約0.7円から7円へと引き上げられます。
また、日本でも有名な「Mt.Gox社」が設立され、開発者による早急の対応で結果的に影響は残りませんでしたが、ビットコインが偽造されたのも同じ時期です。
そして、2011年にTIME誌で初めてビットコインの特集が組まれたことをきっかけに、この日、1BTC=約87円だったビットコインが、数か月で、一気に1,000円台に上昇するのです。
さらに、2012年のヨーロッパ金融危機によって、通貨に依存しないビットコインに注目が集まり、ビットコインは大きく動くことになります。
また、上記のTIME誌の例のように、メディアの影響力の大きさを示したのは、2013年のNHKでの特集からも分かります。
同年10月に1BTC=約13,356円だったビットコインが、放送日には、約123,100円となったのです。
これ以降、2013年の中国での投資急増や、日本でのMt.Gox社の倒産を経て、世界的規模で、ビットコインについての議論が行われるようになります。
2015年には、国際的組織FATF(金融活動作業部会)が、国際協調ガイダンスを公表、日本でも2016年、犯罪収益移転防止法上の修正によって、本人確認義務等を盛り込んだ改正が行われるなど、利用者増加を予測したセキュリティ強化や見直しが国を挙げて行われるようになっていったのです。
2‐3仮想通貨をめぐる日本国内の動き
●日本は諸外国に遅れをとっている!?
上記のように、ビットコインを中心にした仮想通貨は、世界中に広がりを見せています。
しかし、ビットコインに対する規制や利用者数など、各国の動きはさまざまですが、世界の国々に比べ、日本はビットコインに対する法規制の整理や実店舗での利用、サービス展開が若干遅れているのではと感じる人も多いのではないでしょうか。
例にあげるとするならば、2017年1月11日に中国の取引所が、中央銀行の立ち入り検査を受け信用取引のサービスを停止するまでは、中国でのビッコイン市場は、総保有ビットコインの7割とも9割とも推測され、世界最大の取引量と言われていました。
さらに、アメリカの大手ビットコイン取引所である「Coinbase」の利用者数は、400万人以上、それと比較して、日本国内で最大規模のビットコイン取引所と言われる「bitFlyer」の利用者数は、その約10分の1です。
また、アメリカ、カリフォルニア州サンディエゴやカナダのバンクーバーにビットコインATMが設置され、サービスが開始されたのが、2013年。
それに対して、遅れること1年、日本で初めてビットコインATMが導入されたのは、2014年の三重県鈴鹿市に設置された「Lamassu」です。
このような日本のビットコイン利用に対するさまざまな遅延は、実店舗での利用範囲にも見られます。
現在、日本においてビットコインを支払いに利用することができるお店は、わずか150店舗前後です。
日本にも参入している外資系企業のスターバックスやバーガーキングは、ビットコインで支払いが可能。
日本企業であるファミリーマートは、台湾の全3071店舗においてビットコイン決済が可能になっているのです。
それでは、日本ではどうかというと、日本国内に店舗があるにもかかわらず、上記のどの企業もビットコインでの支払いには対応していません。
しかし、2016年にDMM.comがビットコイン決済を採用したのを皮切りに、ビットコイン決済サービスである「coincheckpayment」の導入企業数は、2016年時点で1000社を突破するなど、実店舗以外の場所で前年に比べ約7倍の伸びを見せているのも事実です。
●「仮想通貨」をめぐる政府の動き
また、海外では、急速に成長を見せる仮想通貨の広がりを受けて、2015年を境にさまざまな国がビットコインについての法の整備を行ってきました。
ヨーロッパでは、欧州連合司法裁判所が、ビットコインは税法上、付加価値税を免除するとし、商品としての扱いから、通貨のような取り扱いへと変化し、アメリカ、イギリス、南米、ドイツ、オーストラリアなども次々に、仮想通貨に関する法を整理、利用に対するセキュリティ強化と共に緩和策が取られていったのです。
一方、ビットコインの各国の勢いとは別に、2014年、日本政府は、ビットコインには法律上の強制通用力はなく、通貨には該当しないという見解を示していました。
これは、参議院議員大久保勉氏のビットコインに関する質問の政府側の見解です。
さらに、2014年の「Mt.Gox社」の破綻を受け、2015年、ビットコインの返還を求めた顧客らに対し東京地裁は、ビットコインは所有権の対象とならないと示し、日本のビットコインに対する諸外国との温度差が露わになりました。
仮想通貨による世界的規模の経済の動きに、日本が諸外国から大きく遅れを取った要因が、「Mt.Gox社」の一連の問題によるものであったことは否めませんが、それと同時に、仮想通貨関連の法の整理が遅々として進展してこなかったということも、その大きな原因となっていたのです。
このように、ビットコインに対して、後ろ向きな態度をとっていた日本ですが、諸外国に遅れること数年、2016年3月に仮想通貨に対する初めての法決議案が閣議決定されたのです。
その後、同年5月には、仮想通貨に対する規制を盛り込んだ改正資金決済法が成立、この「仮想通貨法」は、今年度施行予定となっています。
この決定によって、仮想通貨は「決済手段」としての位置づけがなされ、「通貨」とは一線を画すものの、利用者にとっては、商品やサービスへの支払いや法定通貨との交換など公的に利用できる手段として利用することができる「財産的価値」として認められるようになったのです。
このように仮想通貨が、決済手段や法定通貨との交換に使うことができると正式に認められることによって、日本国内での仮想通貨利用にも弾みがつくことは間違いありません。
それによって、国内の経済の動き、さらには消費者の日常生活にまで仮想通貨が入り込んでくることは時間の問題でしょう。
今年予定されている「仮想通貨法」施行を前に、私たち自身も、受け身の体制から、変化を前向きにとらえ、自分のものとして仮想通貨を理解できるよう備えることが必要でしょう。
3.フィンテックで何が変わるのか?知っておきたいフィンテックの基礎知識
先にも挙げたように、仮想通貨やそれらを代表するビットコインの話題の中で、同時によく聞かれるのが、「フィンテック」という言葉です。
この仮想通貨と「フィンテック」が同時に話題に上るのは、仮想通貨の最先端のシステムである「ブロックチェーン」と「分散型元帳」が、急成長を見せる「フィンテック」のサービスを支えるキーテクノロジーの一つだからなのです。
では、そもそもフィンテックとはいったいどのようなもので、自分たちの生活とどのように関係しているのでしょう。
3-1フィンテックとはいったい何?国内のフィンテック事情とその歴史
●フィンテックの国内事情とその歴史
「フィンテック」という言葉をよく耳にするようになったのは、ごく最近のこと、そう思われる方が、多いのではないでしょうか。
それもそのはず、日本国内において、新聞や雑誌などさまざまなメディアで取り上げられるようになり、一般の消費者が、その言葉を目にするようになったのが、2015年以降のことだからです。
ただ、それまでは「フィンテック」は存在しなかったのか?と言えばそうではありません。
現在の言葉の意味よりも狭義であったものの「フィンテック」という言葉自体は、アメリカの金融業界では既に10年以上前に使われていました。
現在、「フィンテック」という用語は、従来の金融機関では想像もできなかったような多種多様なサービスを含んでいますが、10年以上前は、銀行の会計処理システムや出入金自動化機(ATM)ネットワーク、営業店端末など銀行業務の中核を担う情報通信技術のみをそのように呼んでいたのです。
このように書くと、「フィンテック」は、銀行などの金融関連機関によって開発されたのだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそうではありません。
初めて「フィンテック」サービスを事業化し提供するようになったのは、ベンチャー企業です。
企業に安定を求めてきた日本人にとって、ベンチャー企業の印象は、冒険そのものなのではないでしょうか。
しかし、Apple、Google、Youtube、Facebookと聞くとどうでしょう。
これらのサービスや企業は、もともと全てベンチャービジネスでした。
アメリカでは、ベンチャー企業は大きな飛躍の可能性を秘めた宝庫なのです。
「フィンテック」において、世界中を牽引してきたのが、シリコンバレーで生まれたベンチャー企業です。
「フィンテック」は、1998年、ネットショッピングの決済サービスやネットオークションなどの個人間の送金サービスを事業化したベンチャー企業「PayPal」によってはじめられたと言われています。
その後、このようなフィンテック・ベンチャーは、スマートフォンの決済サービス、インターネットを利用した国際送金サービス、資金調達のクラウドファンディングなどさまざまなサービスを生み出し、それぞれが急成長を見せているのです。
拡大するフィンテック・ベンチャーの成功は、2013年に40億5,000万ドルだった投資額が2014年には、120億2,100万ドルへと急上昇した世界のフィンテック・ベンチャー企業への投資額の推移を見ても明らかです。
この数字は、多くのフィンテック・ベンチャー企業が、成功を収めたことによってその事業に注目が集まったことを示しています。
どんなに素晴らしい技術を発表してもベンチャー企業が成長できない日本の土壌に比べ、どのような企業にも成功のチャンスが与えられるアメリカの環境こそが、経済を大きく引き上げ、フィンテックを牽引してきた所以です。
ここでも、日本は諸外国に遅れを取っていると見る方もいるでしょう。
このように日本は、新参者を受け入れるまでに時間がかかり、若者に投資をして成長させようという思想が希薄で、何事においても慎重であることによって、進歩に遅れが見られるのです。
これに加え、金融商品取引法や銀行業法などの決済サービスへの規制が「フィンテック」の導入、発展を妨げる大きな障壁となってきたということも否めません。
上記のように、情報通信技術を駆使し、次々と生み出される海外の新システムと成功を俯瞰した後、日本が本格的にフィンテックに乗り出したのが、2015年でした。
2016年に仮想通貨についての法の整備に中核を置いた動きを政府が見せたことは既述の通りですが、前年の2015年は、「フィンテック」への姿勢を明確にし、関係省庁はもとより業界もその取り組みに挑んだ年だったと言えるでしょう。
具体的には、2015年2月に楽天株式会社主催で開催された「楽天カンファレンス」には、フィンテックの最前線で活躍する国内外の著名な起業家・有識者が集結するとあって、大変注目が集まりました。
同年、5月には「金融商品取引法」の改正によって、金融機関によるフィンテック参入が可能になり、同月に金融庁は、金融審議会において、銀行業法の面からも規制緩和への議論を展開いるのです。
6月には三菱UFJ銀行が「Fintechchallenge」を開催し、コンテストによって新たなフィンテックシステムの発掘と事業化を企業が推進していく姿勢を見せました。
翌7月には、富士通が「FinancialInnovationForJapan(ファイナンシャルイノベーションフォージャパン)」を設立。
そして、9月には金融庁が行政方針に「IT技術の進展による金融業・市場の変革への戦略的な対応」を掲げ、FinTechへの対応方針を明らかにし、10月には、経済産業省が、フィンテック研究会(産業・金融・IT融合に関する研究会)を発足させたのです。
また、同月1日には、ベンチャー企業20社などが「FinTeck協会」を設立。
同年12月には自民党が「フィンテック推進議員連盟」を発足し、同じ月に、金融庁が「Fintechサポートデスク」を設置したのです。
さらに、翌2016年には、日本銀行が、決済機構局内に「フィンテックセンター」を設立するなど、2015‐2016年初頭にかけては、日本がフィンテックへの重要性を意識した時代でもありました。
●「フィンテック」とはいったい何?
では、そもそも「フィンテックとは」どのようなものなのでしょうか?
「フィンテック」は、英語表記で「FinTeck」と書きます。
Finance(金融)の「Fin」×Technology(技術)の「Teck」=「FinTeck」
このように、「FinTeck」は、ファイナンスとテクノロジーの合成によってつくられた造語です。
また、「Teck」(Technology)の部分は、「IT」や「ICT」を指しています。
ちなみに、「IT」は、informationtechnology。
日本語に訳すと、「情報技術」です。
「ITC」は、I=Information、C=Communication、T=Technologyの三つの頭文字からなり、正式には、「InformationandCommunicationTechnology」の略で日本語では、「情報通信技術」と呼ばれているものです。
そして、造語のイメージと「FinTeck」から具体例を導き出すとすれば、「Finance×Technology=FinTechサービス」で、「決済×インターネット=モバイル決済」「貨幣×ブロックチェーン=Bitcoin」「送金×スマートフォン=海外送金」と示すと分かりやすいでしょうか。
さらに、「フィンテック」の発展には、以下3つの技術が背景となっていることも忘れてはなりません。
1つ目に、ビットコインのシステムである「ブロックチェーン」と「分散型元帳」。
2つ目に、AI(人工知能)やビッグデ~タ分析。
3つ目に、スマートフォンです。
今から30年前、携帯電話は、一部のお金持ちの持ち物でした。
大きく重いその電話は、値段も形も、とてもポケットに入れて携帯できるような気軽なものではありませんでした。
通話、それだけの用途のために大変な思いをしていたものが、今ではスマートフォン一つで、電話のみならず、メールはもちろんのこと、写真や動画を撮って保存し、重いデータも送信可能になりました。
さらに、ゲームや映画、お金の支払いやさまざまなデータのやり取りなど、アプリ(Applicationソフト)をダウンロードするだけで、その用途も可能性も大きく広がるようになったのです。
銀行がインターネットバンキングを始め、一般に利用されるようになっていたのも10年ほど前の話です。
また、10年前の携帯電話で、現在のような、動画やゲーム、音楽をダウンロードしようとしたら、携帯電話自体が、キャパシティーオーバーで大変なことになってしまったのではないでしょうか。
通信技術の進歩の背景を見ると分かるように、「フィンテック」は、特に「ICT」の飛躍的な進歩によって開発されたパソコンやスマートフォン、タブレット端末などの情報機器の発展によって利用できるようになり、それらの技術の進歩と共に進化を続けるものなのです。
3‐2フィンテックで私たちの生活はどのように変わるのか?
前述したように、「フィンテック」という言葉が、10年以上前に登場した時と現在とを比較すると、情報通信技術の発達と共に、その言葉が含む意味は広く拡大しています。
では、金融の基本的なテクノロジーシステムのみを指す言葉だった「フィンテック」は、この10年で、どのように変化してきたのでしょうか?
実はその変化は、同時に、私たちの生活の変化にもつながるものなのです。
現段階における「フィンテック」は、10年前の金融における基本的なシステムを指す既存の意味を中核にして、その輪を広げ、多種多様なサービス展開を見せています。
フィンテック関連のサービスを個人の生活に影響があるものを中心に整理してみると、現在のところ「決済」「融資」「送金」「投資」「情報管理」「保険」の6分野に分けることができます。
その6分野のそれぞれには、具体的にどのようなサービスがあるのかを簡単に見ていきたいと思います。
●「決済」
「決済」には、支払い口座の統合、モバイル決済などのキャッシュレス決済と仮想通貨や電子マネー、海外送金などの電子決済テクノロジーのサービスが含まれます。
上記でも触れたように、ネットショッピングの決済サービスやネットオークションなどの個人間の送金を可能にしたベンチャー企業「PayPal」のサービスもここに含まれます。
「○○Pay」や「○○Wallet」と言ったCMや言葉をよく耳にするようになったと思いますが、現金を持ち歩かずに近所に買い物に出かけ、スマートフォン一つで旅行に出かける時代は、実はもう既に身近にあるのです。
●「融資」
「融資」を金融機関から受けるためには、これまで、より条件の良い金融機関を選択するために膨大な情報を検索し、書類を準備し、申し込みをした上で、審査を受け、融資を受けるという流れがありました。
このように特に消費者側には、時間も労力も負担の多いものでありましたが、フィンテックが融資を仲介するサービスをオンラインで行うことによって、融資の一連の流れがよりスムーズになり、多くの人が好条件で借り入れできるようになります。
「お金を借りたい」という人と「この条件でお金を貸したい」という人の個人対個人のマッチングをフィンテックの融資仲介によって行い、融資も返済もフィンテックを利用することで手数料を抑えることができる点も利点です。
金融機関側にとっても、時間やお金をかけて委託していた審査を顧客のビックデータ解析などによって、短時間で資金をかけずにできるようになるため、大変便利になります。
個人や企業が、資金を集めるためのクラウドファンディングや人材雇用などのサービスもこの一部です。
●「送金」
上にも記したように、これまでの金融機関を通した海外への送金には、手数料の面でも時間的にも利用者負担が多かったのですが、フィンテックのサービスが介入することで、オンラインで個人対個人をつなぎ、安価な手数料で、短時間で送金することが可能になるのです。
●「投資」
「投資」には、AI(人工知能)を活用したロボットアドバイザーなどの投資家向けサービスや高性能なWEBアクセス解析ツールを利用した金融企業向けサービスが可能になります。
これまで、お金のかかった投資ポートフォリオなど時間をかけずに作成してくれるため、管理や確認が簡単にできるようになります。
また、AI(人工知能)を活用したサービスが可能になることで、初心者でも利用しやすく、安価でサービスを享受することができるようになります。
極端な例では、ロボットアドバイザーは、資産運用の助言だけではなく、全てお任せもできるのです。
例えば、投資できる金額をロボットアドバイザーに預ければ、自分は何もしない間に、周囲の動きや経済の流れを細かくとらえながら、リスクを避け、可能な限り大きなリターンを目指し、資産運用をしてくれるのです。
●「情報管理」
私たちの生活の例から最もわかりやすい「情報管理」は、家計簿でしょう。
これまで、大量のレシートや領収書を保管したり、ノートやパソコンに入力していたものが、フィンテックとカード会社、金融機関、さまざまな企業が連携していくことで、自分で書いたり、入力する手間なく、細かく正確に自動で家計の収入や支出を管理してくれるようになります。
さらに、上記のように家計簿にフィンテックサービスを利用することによって、どの部分の出費が多くて赤字になるのか、どのような点に留意したお金の使い方が家計負担を軽減させるのかなどが分かるようになります。
自分では、発見できない問題点や専門家を頼むとコストがかかり、なかなか改善できなかった家計管理が、フィンテックによって個人の家計をマネジメントし、家計の問題の発見に加え、改善策も提案してくれるようになるのです。
●「保険」
「保険」では、フィンテックのキーシステムであるビッグデータの解析と活用によって、消費者が、より自分に合った保険を選択できるようになります。
これまでの運転歴や利用者本人の健康状態、アクシデント歴や車の状態などさまざまな情報を瞬時に読み取り、多くの保険商品の中から最適なものとマッチングさせ保険料を提示してくれるのです。
さらに、フィンテックサービスを利用することで、保険料算定などの時間やコストを抑えられ、結果的に、消費者も低コストで保険を加入することが可能になるという仕組みです。
また、健康管理のウェアラブルデバイス(時計型の健康管理デバイス)を利用することで、加入前の健康診断がなくなる人も増え、時間もコストもカットされることになるでしょう。
健康管理のウェアラブルデバイスによって何が分かるかと言えば、その機種にもよりますが、心拍数のデータやさまざまな病気の兆候、既往症のある人の健康についてもチェックすることができるのです。
これによって、消費者のニーズに合った保険商品やより低価格のプランを見つけることができ、健康な人は割引などのサービスを受けることができるなど時間的にもコスト面でも便利になることは間違いありません。
終わりに~フィンテックと10年後の未来~
「フィンテック」は未来のもの。
そのように思われていた方も多いのではないでしょうか?
しかし、これまで述べてきたことを見てみると、それは、未来のものでも、近い将来のものでもなく、実は私たちの生活に既に入り込んで来ているということが分かるのではないでしょうか。
幅広い世代から支持を受け、利用者の多いスマートフォンは、フィンテックそのものではありませんが、フィンテックのサービスがたくさん詰まった便利なアイテムです。
そのアイテムをフィンテックのサービスが入り込んでいるとは知らずに、便利さを享受してきた方は多いでしょう。
2017年に入り、金融庁は仮想通貨の「ブロックチェーン」技術について海外の金融関連機関と連携して国際的な共同研究を行うと発表しています。
さらに、三大メガバンクと言われる銀行は、既にフィンテック専門部署を起ち上げ、動き出しています。
三菱UFJフィナンシャルグループは、今年中に仮想通貨「MUFJ」を一般向けに発行すると発表し、SMBCグループは、決済業務や融資までを念頭に、ネット上でたくさんのお店を出店する「仮想商店街」なるものを構想、みずほフィナンシャルグループもビックデータを活用した新サービス開発に取り組んでいます。
「フィンテックがあれば、銀行がなくてもビジネスはできる」と言われる中で、フィンテックをどのように活用し、取り込むことができるのかを考え、それぞれが新たな戦略に乗り出しているのです。
このように、大企業はもとより、動きが遅いと言われてきた政府までもが、本腰を入れてフィンテックと歩んでいく覚悟を決めています。
今後、もしかしたら、日銀が仮想通貨を発行するという日もやってくるのかもしれません。
さらに、上記で携帯電話を例に出して、現代における技術の進歩の早さを既述したように、現代の情報通信技術は、つい10年前、いいえ、5年前の出来事が既に過去のものとして扱われ、ほんの少し前の常識はすぐに通用しなくなってしまう時代なのです。
オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン氏が、数年前に"THEFUTUREOFEMPLOYMENT:HOWSUSCEPTIBLEAREJOBSTOCOMPUTERISATION?"という論文に、10-20年後にAIなどのコンピュータにとって代われる職業のランキングを発表しています。
オズボーン氏の見解では、銀行の融資担当者、保険の審査担当者、スポーツの審判員、電話オペレーターなど、さまざまな職業がなくなるというのです。
このような論からも推測できるように、ほんの数年の間に、私たちの生活や価値観を一気に変えてしまう変革が起こるでしょう。
一般の消費者も、油断していると一気に波に飲み込まれ、あまりの時間の動きの早さに自分が立っている場所さえわからなくなってしまうかもしれません。
10年後も今と同じ生活をしたいと思っていても、情報通信技術によって、自分の意志に反した生活を余儀なくされるかもしれないのです。
科学を操作していたはずの人間が知らない内に操られていた。そのようなことにならないよう、ここでしっかりと、情報通信技術がさらに進展した未来について考え、そこから飛び出すさまざまな技術について自分なりに理解しておくということは、テクノロジーの進展が今後ますます加速が予測される現代において、大切なことのひとつなのではないでしょうか。